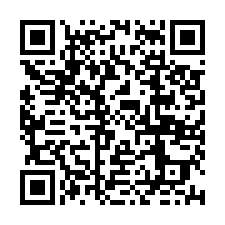|
|
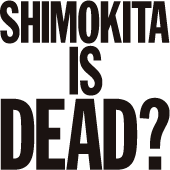 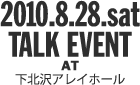
佐高信 
黒田征太郎
ライブチケットのご予約 チケットぴあ ローソンチケット ビグトリィ |
「うるさくてもシズカ 67」シモキタ 大石静私の通っていた高校は、小田急線沿線にあり、学校の帰りに途中下車しては、下北沢の町をうろうろしていた。 細い路地には何軒もの木綿の生地屋が並んでおり、そこでかわいいプリントのキルティング生地を買い、オリジナルのトートバッグを縫って、高校に持ってゆくのが、当時私の学校では流行っていた。 バッグは直線縫いだけで出来るし、キルティングだと裏もつけなくていいので、とても簡単で、みんな作っていた。お弁当袋とセットにしたりして……。 大学を出て舞台女優を志すようになってからは、下北沢で暮らしていたようなものである。超マイナー演劇人だった私の思い出は下北沢の町につきると言っても過言ではない。 小劇場ブームが訪れ、下北沢には小さな劇場がいくつも出現した。その中で残っているのはザ・スズナリくらいだろうか。今は消防法などで小さな劇場に大勢のお客を入れることは出来ないが、当時は2階にある劇場の床が抜けるほどのお客が入り、みんな酸欠状態になりながら芝居を見たものだ。 三谷幸喜作・演出の芝居を初めて見たのは、駅前劇場である。50人も入れば一杯になるような小屋だったが、三谷さんの才能は輝いていたし、西村雅彦などもセクシーな若手の二枚目役者で目立っていた。この劇団はイケると思ったことを思い出す。 私が最初に所属した劇団の稽古場は、下北沢のキャバレーの跡を改造したもので、ロッカーの中からオトナのおもちゃがゴロゴロ出てきたりして、いかがわしくもあり刺激的でもあった。 稽古の後は毎晩仲間と飲み、この時代に私は、自分が人よりお酒に強いことを知った。酎ハイという飲み物と、モツの煮込みという料理を知ったのもこの町だ。 そのうち駅前の大きな空き地に本多劇場が出来、まさに下北沢はマイナーメジャーな演劇のメッカになった。本格的メジャーになるより、マイナーメジャーの方がカッコイイのだと私たちは語り合った。それは言い訳だったようにも思う。 これから世に出ようとする者のエネルギーが町に炸裂していたもの。本多劇場に初めて出た時の晴れがましさを、私は今も忘れない。 次第に小劇場ブームは去り、小さな小屋は姿を消して、スズナリぐらいになったが、木造の建物が路地にひしめき合い、歩いてしか通れない不思議な町の様子と、下北独特の洋品店、古典的喫茶店などの文化は、時代を移りながらも、独特な価値を生み出している。 世田谷の家を手離してから、あまり下北沢には行かなくなったが、下北沢が再開発されることになり、住民が反対運動を起こしているという話しを聞いた。細い路地は災害の時に被害を大きくするとか、開発をする側にもをそれなりの理由があるのはわかるが、駅前商店街は日本独特の文化である。 人々の日々の営みが息づいているような商店街をなくし、下北のような独特の町をつぶして、大きな道路と高層ビルが立ち並ぶお台場のような町にすることが、人々の暮らしをいかに貧しくするか……。開発派は今一度考えてほしいと思う。災害被害を少なくする方法を、何もかもなぎ倒さないで考えてほしい。再開発で景気を活性化するという考えもあるが、どこもかしこもお台場のようになって、日本人はしあわせになるとは思えないからだ。 (婦人公論2010.7122号 より) |
 TOPICS2010/8/1よしもとばななさんのエッセーを掲載しました。 2010/8/2大石静さんのエッセーを掲載しました。 2010/8/5筒井ともみさんのエッセーを掲載しました。 「SHIMOKITA VOICE 2010」 |
Copyright (C) 2007-2010 SHIMOKITA VOICE All rights reserved.